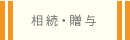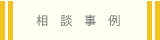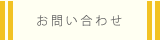2010年09月16日
ちゅくいむじゅくい 風土と建築
沖縄県立美術館で開催中の
「ちゅくい むじゅくい 風土と建築」展へ行ってきました。
「〜”ちゅくいむじゅくい”は古来生活文化の中で育まれた言葉で、ちゅくい(創る)と むんじゅくい(造る)を合わせて、創造・creationの意味だという。そして、それには知恵(じんぶん)が働いていることが必須条件であるともいっていた。〜」
沖縄タイムス 2010年9月10日 県民キュレーター展に寄せて 佐久川一 より
この日は「ちゅくいむじゅくいで考える地域の未来」と題して、山原ものづくり塾の島袋氏と県内で活躍中の建築家の方々が参加するシンポジウムが開催されました。
沖縄の風土に適した家作り、本当に家族にとって地域にとって地球にとっていい家作りってどういうことなのだろう?と考えさせられました。
現在の「都市追求型社会」とは違い、昔は家に家畜を飼い、畑を耕し、大きな行事は地域の人々と協力して行うという地域のコミュニティや風土を活かした「循環型社会」でした。
「循環型社会」とはとにかく知恵を使うものです。
作物をどうやって育てるか、家畜をどうやって育てるか、コミュニティを潤滑に運営するにはどうするか。
知恵を振り絞らないと生きていくことはできません。
その代わりにお金は最小限しかかからないのです。
「都市型追求社会」は非常に便利です。
とにかく快適。気兼ねなく自由に生活できます。ご近所に気を使うこともありません。
日々の生活に知恵を絞らずとも、悠々と暮らせます。
しかし、その暮らしを継続する為には多大な資金が必要となります。
私はファイナンシャルプランナーとして、なぜ生活の基本である家を手に入れる為にこんなにも大金が必要なのか引っかかっていました。
たくさんの知恵を絞れば、もう少し家の価格がお手頃になるのではないか?
家作りやライフプランをもっと真剣に突き詰めていけば、本当に自分たちに合った家というものに巡り会えるのではないだろうか?
パネルディスカッションに参加された建築家さんの
「人は生まれてから15年間の環境がその人の一生を決める」
という言葉がありました。
15年間の環境がその後の人生の無意識の価値観を決めるのです。
だからといって無闇矢鱈に懐古主義に捕われず、技術の進化をちゃんと受け止めることも大事。
大きな波に流されながらも社会や自分の立ち位置に常に違和感を持ち続けるまなざしが必要。
家作りのお話から物事の考え方まで、たくさんのことを勉強できたシンポジウムでした。
シンポジウムの後は企画展も見てきましたよ。
昔から現在までの沖縄の建築の流れが垣間みれます。
写真はもちろん、書物や展示品、そして巨大な作品(見てのお楽しみ)などたくさんの見所がありましたよー。
ご興味のある方はぜひ!
詳細は2010県民キュレーター展のHPをご覧ください。
http://sites.google.com/site/kenmincurator/home


↑クリックすると大きくなりますよ
19日にはワークショップ、23日は歴史的建造物見学、25日は街歩きなどのイベントもあるみたいです。
私も可能な限り参加して、沖縄の建築について勉強したいと思ってます。
「ちゅくい むじゅくい 風土と建築」展へ行ってきました。
「〜”ちゅくいむじゅくい”は古来生活文化の中で育まれた言葉で、ちゅくい(創る)と むんじゅくい(造る)を合わせて、創造・creationの意味だという。そして、それには知恵(じんぶん)が働いていることが必須条件であるともいっていた。〜」
沖縄タイムス 2010年9月10日 県民キュレーター展に寄せて 佐久川一 より
この日は「ちゅくいむじゅくいで考える地域の未来」と題して、山原ものづくり塾の島袋氏と県内で活躍中の建築家の方々が参加するシンポジウムが開催されました。
沖縄の風土に適した家作り、本当に家族にとって地域にとって地球にとっていい家作りってどういうことなのだろう?と考えさせられました。
現在の「都市追求型社会」とは違い、昔は家に家畜を飼い、畑を耕し、大きな行事は地域の人々と協力して行うという地域のコミュニティや風土を活かした「循環型社会」でした。
「循環型社会」とはとにかく知恵を使うものです。
作物をどうやって育てるか、家畜をどうやって育てるか、コミュニティを潤滑に運営するにはどうするか。
知恵を振り絞らないと生きていくことはできません。
その代わりにお金は最小限しかかからないのです。
「都市型追求社会」は非常に便利です。
とにかく快適。気兼ねなく自由に生活できます。ご近所に気を使うこともありません。
日々の生活に知恵を絞らずとも、悠々と暮らせます。
しかし、その暮らしを継続する為には多大な資金が必要となります。
私はファイナンシャルプランナーとして、なぜ生活の基本である家を手に入れる為にこんなにも大金が必要なのか引っかかっていました。
たくさんの知恵を絞れば、もう少し家の価格がお手頃になるのではないか?
家作りやライフプランをもっと真剣に突き詰めていけば、本当に自分たちに合った家というものに巡り会えるのではないだろうか?
パネルディスカッションに参加された建築家さんの
「人は生まれてから15年間の環境がその人の一生を決める」
という言葉がありました。
15年間の環境がその後の人生の無意識の価値観を決めるのです。
だからといって無闇矢鱈に懐古主義に捕われず、技術の進化をちゃんと受け止めることも大事。
大きな波に流されながらも社会や自分の立ち位置に常に違和感を持ち続けるまなざしが必要。
家作りのお話から物事の考え方まで、たくさんのことを勉強できたシンポジウムでした。
シンポジウムの後は企画展も見てきましたよ。
昔から現在までの沖縄の建築の流れが垣間みれます。
写真はもちろん、書物や展示品、そして巨大な作品(見てのお楽しみ)などたくさんの見所がありましたよー。
ご興味のある方はぜひ!
詳細は2010県民キュレーター展のHPをご覧ください。
http://sites.google.com/site/kenmincurator/home


↑クリックすると大きくなりますよ
19日にはワークショップ、23日は歴史的建造物見学、25日は街歩きなどのイベントもあるみたいです。
私も可能な限り参加して、沖縄の建築について勉強したいと思ってます。
Posted by FP事務所エレファントライフ at 15:13│Comments(2)
│FPコラム
この記事へのコメント
なんか、大学の時に読んだ社会学の教科書思い出した笑っ
Posted by 本庄冬武 at 2010年09月16日 22:57
◆トム
そうなんだ? 私はこういうこと、学ばなかったなー。
そうなんだ? 私はこういうこと、学ばなかったなー。
Posted by FPトモリ at 2010年09月17日 21:00
at 2010年09月17日 21:00
 at 2010年09月17日 21:00
at 2010年09月17日 21:00※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。