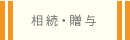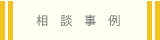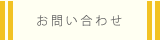2009年08月28日
【不動産】長期優良住宅
平成21年の6月に長期優良住宅の普及の促進に関する法律が施行されました。
これは一定の基準を満たした長期優良住宅には税制上の優遇措置などが受けられる制度で、その目的は欧米や欧州に比べ住宅寿命の短い日本の住宅事情の改善と中古住宅市場の流通促進と言われています。
それでは長期優良住宅に認定されると何がどうお得になるか、具体的に見ていきましょう。
まず住宅取得時に係る税金についてです。
★住宅取得時には
□印紙税
□消費税
■登録免許税
■不動産取得税
などの税金がかかります。
長期優良住宅に認定された場合、この中の■の項目「登録免許税」と「不動産取得税」に特例措置が適用されます。
例えば2000万円の住宅を購入した場合。
◆一般の住宅◆
登録免許税(移転登記) 60,000円
不動産取得税 240,000円
合計 300,000円
◆長期優良住宅◆
登録免許税(移転登記) 20,000円
不動産取得税 210,000円
合計 240,000円
長期優良住宅にすることで6万円節税することができます。
★住宅保有時には
固定資産税が課税され、新築住宅の場合は減額措置があります。
◆一般の住宅◆
固定資産税20万円の場合
新築後5年間は固定資産税が1/2に。
10万円×5年=50万円減税
◆長期優良住宅◆
固定資産税20万円の場合
新築後最大7年は固定資産税が1/2に。
10万円×年=70万円減税
長期優良住宅にすることで20万円節税することができます。
★住宅ローン控除
所得税から控除される住宅ローン控除も変わってきます。
※2000万円のローンを組み、毎年100万円ずつ返済している場合
◆一般の住宅◆
控除率1%
1年目 19万円
2年目 18万円
3年目 17万円
・
・
・
10年目 10万円
控除合計 145万円
◆長期優良住宅◆
控除率1.2%
1年目 22.8万円
2年目 21.6万円
3年目 20.4万円
・
・
・
10年目 12万円
控除合計 174万円
長期優良住宅にすることで29万円節税することができます。
以上を合計すると、一般の住宅よりも長期優良住宅の方が55万円節税できるという結果になりました。
※わかりやすくするためにかなりアバウトな単純計算となっております。個々のケースによって結果は変わってきます。ご了承ください。
ちなみに長期優良住宅を建てる場合、一般の住宅よりも建設費が2割UPすると言われています。
2,000万円の住宅であれば400万円のUPで2,400万円となります。
減税のメリットがあるとはいえ、建設費の増加分まで賄うことは難しいようです。
今回の法律は欧米や欧州などと比べて格段に短い日本の住宅の寿命を長くするとともに、中古住宅流通の促進と言った側面もあります。
しかし中古住宅の増改築にまつわる規制が厳しい昨今において、この法律が中古住宅の流通促進に繋がるか難しいところですね。
個人的には大賛成!です。だって住宅ってこんなにお金かけるんだからちゃんと手入れしてずーっと大事にしていきたいし、次の世代まで残していきたい。
むやみやたらに造って壊しての時代はもう終わったと思っています。
あとは法の整備! 今後中古住宅の流通を取り巻く環境がどう変わるか期待しています。

今日もこんな時間~! 早起きしなきゃなのにな。太陽が昇らないうちに自転車でへーこら帰ります。
あ、ちなみに車注文しちゃいましたよ。何を買ったかはまた後日。
それまでは14年目のスターレット(傷、凹み多数)を可愛がってあげないとなので、明日からは車通勤に戻ります!
(単に自転車に疲れただけ(笑))
これは一定の基準を満たした長期優良住宅には税制上の優遇措置などが受けられる制度で、その目的は欧米や欧州に比べ住宅寿命の短い日本の住宅事情の改善と中古住宅市場の流通促進と言われています。
それでは長期優良住宅に認定されると何がどうお得になるか、具体的に見ていきましょう。
まず住宅取得時に係る税金についてです。
★住宅取得時には
□印紙税
□消費税
■登録免許税
■不動産取得税
などの税金がかかります。
長期優良住宅に認定された場合、この中の■の項目「登録免許税」と「不動産取得税」に特例措置が適用されます。
例えば2000万円の住宅を購入した場合。
◆一般の住宅◆
登録免許税(移転登記) 60,000円
不動産取得税 240,000円
合計 300,000円
◆長期優良住宅◆
登録免許税(移転登記) 20,000円
不動産取得税 210,000円
合計 240,000円
長期優良住宅にすることで6万円節税することができます。
★住宅保有時には
固定資産税が課税され、新築住宅の場合は減額措置があります。
◆一般の住宅◆
固定資産税20万円の場合
新築後5年間は固定資産税が1/2に。
10万円×5年=50万円減税
◆長期優良住宅◆
固定資産税20万円の場合
新築後最大7年は固定資産税が1/2に。
10万円×年=70万円減税
長期優良住宅にすることで20万円節税することができます。
★住宅ローン控除
所得税から控除される住宅ローン控除も変わってきます。
※2000万円のローンを組み、毎年100万円ずつ返済している場合
◆一般の住宅◆
控除率1%
1年目 19万円
2年目 18万円
3年目 17万円
・
・
・
10年目 10万円
控除合計 145万円
◆長期優良住宅◆
控除率1.2%
1年目 22.8万円
2年目 21.6万円
3年目 20.4万円
・
・
・
10年目 12万円
控除合計 174万円
長期優良住宅にすることで29万円節税することができます。
以上を合計すると、一般の住宅よりも長期優良住宅の方が55万円節税できるという結果になりました。
※わかりやすくするためにかなりアバウトな単純計算となっております。個々のケースによって結果は変わってきます。ご了承ください。
ちなみに長期優良住宅を建てる場合、一般の住宅よりも建設費が2割UPすると言われています。
2,000万円の住宅であれば400万円のUPで2,400万円となります。
減税のメリットがあるとはいえ、建設費の増加分まで賄うことは難しいようです。
今回の法律は欧米や欧州などと比べて格段に短い日本の住宅の寿命を長くするとともに、中古住宅流通の促進と言った側面もあります。
しかし中古住宅の増改築にまつわる規制が厳しい昨今において、この法律が中古住宅の流通促進に繋がるか難しいところですね。
個人的には大賛成!です。だって住宅ってこんなにお金かけるんだからちゃんと手入れしてずーっと大事にしていきたいし、次の世代まで残していきたい。
むやみやたらに造って壊しての時代はもう終わったと思っています。
あとは法の整備! 今後中古住宅の流通を取り巻く環境がどう変わるか期待しています。

今日もこんな時間~! 早起きしなきゃなのにな。太陽が昇らないうちに自転車でへーこら帰ります。
あ、ちなみに車注文しちゃいましたよ。何を買ったかはまた後日。
それまでは14年目のスターレット(傷、凹み多数)を可愛がってあげないとなので、明日からは車通勤に戻ります!
(単に自転車に疲れただけ(笑))
Posted by FP事務所エレファントライフ at 03:51│Comments(2)
│FPコラム
この記事へのコメント
お久しぶりです!かなり(笑)
長期優良住宅、社内でも議題に上がっています。
現時点ではどれぐらいコストアップするかが焦点ですね~。
P.S
FP持っていますが、あまり使いこなせてません(爆)
また勉強しにきまーす。
長期優良住宅、社内でも議題に上がっています。
現時点ではどれぐらいコストアップするかが焦点ですね~。
P.S
FP持っていますが、あまり使いこなせてません(爆)
また勉強しにきまーす。
Posted by てぃーだ営業MEN! at 2009年09月10日 17:45
at 2009年09月10日 17:45
 at 2009年09月10日 17:45
at 2009年09月10日 17:45■てぃーだ営業MEN!さん
覚えていてくださって嬉しいです♪ 本当にご無沙汰しております。
長期優良住宅や瑕疵担保責任10年や、今年は建設業界変化の年となりそうですね。
現場に立つ方は本当に気苦労が多いと思います。
暑さに負けずに頑張ってくださいね☆ 応援してます!
覚えていてくださって嬉しいです♪ 本当にご無沙汰しております。
長期優良住宅や瑕疵担保責任10年や、今年は建設業界変化の年となりそうですね。
現場に立つ方は本当に気苦労が多いと思います。
暑さに負けずに頑張ってくださいね☆ 応援してます!
Posted by FPトモリ at 2009年09月11日 03:36
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。