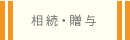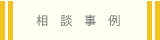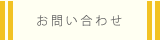2008年12月25日
所得格差
県民所得格差、4年連続で拡大
内閣府は2008年2月5日、05年度の「県民経済計算」を発表した。それによると、都道府県の住民1人当たりの所得額(県民所得)は全国平均で前年度比2.5%増の304万3000円となり、2年連続で上昇した。都道府県別に見ると、最も所得が多かったのが東京都の477万8000円で、最下位は沖縄県の202万1000円だった。東京と沖縄の所得格差は2.4倍で、格差は4年連続で拡大した。
http://www.j-cast.com/2008/02/06016406.html
県民所得208万9000円/06年度/0・5%減で全国格差広がる
県企画部統計課は十六日、二〇〇六年度の県民経済計算の概要を公表した。県内総生産は、名目で前年度比0・1%増の三兆六千八百七十六億円。経済成長率は名目で0・1%増加、物価変動を勘案した実質で0・6%伸びた。
県民所得総額は二兆八千五百八十四億円で前年並み。県民所得を総人口で割った一人当たり県民所得は、前年度比0・5%減の二百八万九千円。一人当たりの国民所得を100とした場合、県民一人当たりの所得水準は71・5。格差は前年度より1・7ポイント広がった。
統計課によると、〇六年度は一部の産業が原油など原材料価格高騰の影響を受けたものの、入域観光客数が過去最高を更新するなど、観光関連産業が県経済をけん引した。雇用者報酬の改善、株価・金利上昇に伴う財産所得の上昇を背景に、民間需要が堅調に推移。同課は「全体としては〇五年度に引き続き回復基調をたどった」と分析している。
県内総生産(名目)を産業別にみると、第三次産業は前年度比0・3%増の三兆三千三百四億円、第二次産業が同2・4%減の四千三百五十二億円、第一次産業は同0・2%増の六百九十四億円。
第三次産業で増加したのは、観光などのサービス業(2・0%)、不動産業(2・7%)など。電気・ガス・水道業は燃料費高騰によるコスト高で5・0%の減。卸売・小売業、金融・保険業、運輸・通信業もそれぞれ落ち込んだ。
第二次産業では製造業が原油高騰などの影響を受け1・6%減。建設業は公共工事の落ち込みにより2・8%減。第一次産業では農業が生乳、肉用豚、鶏卵の生産が落ち込み、1・0%減。水産業は養殖モズクが増え5・5%伸びた。
雇用者報酬は0・3%増の一兆七千四十九億円。財産所得は14・3%増の二千三百八十八億円、企業所得は3・8%減の九千百四十七億円だった。
http://www.okinawatimes.co.jp/news/2008-12-17-M_1-002-1_001.html
所得格差が拡大しています。
1位の東京と最下位の沖縄を比較するとなんと倍以上も開きがあるんですね。
先日事務所に遊びにいらっしゃった某外資系企業支店長(関東出身)の方が、沖縄の文化や経済が「本土並み」を目標に突っ走っているのにとても違和感を感じる、と仰っていました。
以前海邦総研のセミナーに参加した際、沖縄県民でストレスを感じていない方が60%以上いるという結果に少し驚きましたが、経済の度合いと生活満足度って比例するものではないんだな、と痛感しました。
経済的にゆとりのない生活はとても不安です。
しかし経済的に余裕があるからと言ってストレスが無くなるかというとそうでもないようです。
きっと「バランス」なんでしょうね。
良いバランスを保つにはやはりお金と上手に付き合うことが大事。
金融知識の取得をもっと積極的におこなっていきましょう。

下記はつれづれ日記です。ご興味のある方だけどうぞ。
内閣府は2008年2月5日、05年度の「県民経済計算」を発表した。それによると、都道府県の住民1人当たりの所得額(県民所得)は全国平均で前年度比2.5%増の304万3000円となり、2年連続で上昇した。都道府県別に見ると、最も所得が多かったのが東京都の477万8000円で、最下位は沖縄県の202万1000円だった。東京と沖縄の所得格差は2.4倍で、格差は4年連続で拡大した。
http://www.j-cast.com/2008/02/06016406.html
県民所得208万9000円/06年度/0・5%減で全国格差広がる
県企画部統計課は十六日、二〇〇六年度の県民経済計算の概要を公表した。県内総生産は、名目で前年度比0・1%増の三兆六千八百七十六億円。経済成長率は名目で0・1%増加、物価変動を勘案した実質で0・6%伸びた。
県民所得総額は二兆八千五百八十四億円で前年並み。県民所得を総人口で割った一人当たり県民所得は、前年度比0・5%減の二百八万九千円。一人当たりの国民所得を100とした場合、県民一人当たりの所得水準は71・5。格差は前年度より1・7ポイント広がった。
統計課によると、〇六年度は一部の産業が原油など原材料価格高騰の影響を受けたものの、入域観光客数が過去最高を更新するなど、観光関連産業が県経済をけん引した。雇用者報酬の改善、株価・金利上昇に伴う財産所得の上昇を背景に、民間需要が堅調に推移。同課は「全体としては〇五年度に引き続き回復基調をたどった」と分析している。
県内総生産(名目)を産業別にみると、第三次産業は前年度比0・3%増の三兆三千三百四億円、第二次産業が同2・4%減の四千三百五十二億円、第一次産業は同0・2%増の六百九十四億円。
第三次産業で増加したのは、観光などのサービス業(2・0%)、不動産業(2・7%)など。電気・ガス・水道業は燃料費高騰によるコスト高で5・0%の減。卸売・小売業、金融・保険業、運輸・通信業もそれぞれ落ち込んだ。
第二次産業では製造業が原油高騰などの影響を受け1・6%減。建設業は公共工事の落ち込みにより2・8%減。第一次産業では農業が生乳、肉用豚、鶏卵の生産が落ち込み、1・0%減。水産業は養殖モズクが増え5・5%伸びた。
雇用者報酬は0・3%増の一兆七千四十九億円。財産所得は14・3%増の二千三百八十八億円、企業所得は3・8%減の九千百四十七億円だった。
http://www.okinawatimes.co.jp/news/2008-12-17-M_1-002-1_001.html
所得格差が拡大しています。
1位の東京と最下位の沖縄を比較するとなんと倍以上も開きがあるんですね。
先日事務所に遊びにいらっしゃった某外資系企業支店長(関東出身)の方が、沖縄の文化や経済が「本土並み」を目標に突っ走っているのにとても違和感を感じる、と仰っていました。
以前海邦総研のセミナーに参加した際、沖縄県民でストレスを感じていない方が60%以上いるという結果に少し驚きましたが、経済の度合いと生活満足度って比例するものではないんだな、と痛感しました。
経済的にゆとりのない生活はとても不安です。
しかし経済的に余裕があるからと言ってストレスが無くなるかというとそうでもないようです。
きっと「バランス」なんでしょうね。
良いバランスを保つにはやはりお金と上手に付き合うことが大事。
金融知識の取得をもっと積極的におこなっていきましょう。
下記はつれづれ日記です。ご興味のある方だけどうぞ。
先日植えたばかりのパクチー(コリアンダー)がわしゃわしゃ増えたので初収穫しました!
ローズマリーはアロマポットで水とともに暖めてアロマオイル代わりに。
ミニトマトもびっくりするくらい大きくなってます。
ガーベラは首が折れてしまったので、花器に水を張って浮かべてみました。
新しい蕾も出ているのでまだまだ楽しめそうです。
昨日はお友達手作りの美味しいクリスマスディナーをいただきながら久々にテレビ(いいとも~明石家サンタ)をガッツリ見ました。
料理上手のお友達からレシピも教わったよ。お正月にでもチャレンジしてみます。
クリスマスプレゼントとして写真のぞうさんまでもらっちゃったよ。
何も用意もしてなかった私は身体でお返し・・・。
得意のマッサージで全身をほぐしてあげました(笑)
1時間くらいかな。お友達が寝入るまで汗をかきかき丁寧にモミモミしましたよー。
張り切って頑張ったせいか今日は私がお疲れ。
仕事終わったら岩盤浴に行って身体をほぐしてこようと思いまーす。
Posted by FP事務所エレファントライフ at 15:48│Comments(0)
│FPコラム
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。