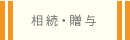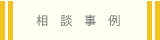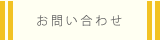› 沖縄のFPファイナンシャルプランナー不動産専門FPのエレファントライフ › ヌチヌスージサビラ!
› 沖縄のFPファイナンシャルプランナー不動産専門FPのエレファントライフ › ヌチヌスージサビラ!2011年04月19日
ヌチヌスージサビラ!
先々週、宜野湾海浜公園で開催されたWhat a Wonderfull Worldに参加してきました。

HY、サンボマスター、モンゴル800などなど豪華メンバー勢揃い!
私はHY→知名定男さん→マルチーズロック→神谷幸一さん→モンゴル800→神谷千尋さん→登川誠仁さん→下地勇さん→新良幸人さん→玉城千春さん(kiroro)→BEGINという流れで観ましたよ。
ていうかあまりにも豪華メンバーが揃い過ぎて、どこのステージに行こうか迷いまくりました。
最後のBEGINさんでは出演アーティストが全員参加して「島人ぬ宝」を大合唱。そこで「ヌチヌスージサビラ」という言葉を聞いてどう言う意味なのか気になっていたのです。
その後調べると、これは戦後の沖縄で活躍した「小那覇舞天さん」の言葉で、「命のお祝をしましょう」という意味でした。
ちょっと長いのですが、詳細を下記に転載しますね。
沖縄県の石川市(いしかわし)は、沖縄本島のほぼ中央にあって、第二次世界大戦後、沖縄で最初にできた市です。それまでは、美里村字石川(みさとそんあざいしかわ)といって人口二〇〇〇人足らずの静かな農村でした。戦争が終わった昭和二十年(一九四五年)、米軍によってここに難民収容所(なんみんしゅうようじょ)が設置され、沖縄各地から戦火に追われたたくさんの人々が集まりました。そのため、石川の人口は数ヵ月で三万人にふくれ上がり、石川市となったのです。
けれども、市になったからといって人々の生活が楽になるわけはありません。人々は、戦争で受けた心の傷を癒(いや)す間もなく、その日その日を何とか生き延びることで精一杯でした。軍の作業に駆り出され、食料と物資を手に入れることに追われて、疲れきり、毎日希望を失ったまま暮らしていました。

そこに突然現れた風変わりな男、それが小那覇舞天(おなはぶーてん)でした。
舞天は本名を小那覇全孝(おなはぜんこう)といい、沖縄県立二中(今の県立那覇高校(なはこうこう))を第一期で卒業し、その後日本歯科医学専門学校(現日本歯科大学)を卒業した歯科医でした。
舞天は仕事で白衣(はくい)を着ているときや家にいるときは、それこそまじめで口数の少ない人でしたが、一歩外に出ると風変わりな男に変わりました。
舞天は、弟子の照屋林助(てるやりんすけ)と毎晩のように、まだ起きている家を見つけては甲高(かんだか)い声で「ヌチヌスージサビラ(命のお祝いをしましょう)」といって入っていきます。「ジャカジャカジャン」と三味線が鳴り響き、歌が始まります。
突然やって来た中年の男が、その場でつくった歌を民謡(みんよう)の節に乗せ、この地方独特の踊りである琉球舞踊(りゅうきゅうぶよう)をくずしたヘンテコな踊りを舞うのですから、みんなはあ然とします。
しかし、やがて舞天のユーモラスな姿に乗せられ、みんなも一緒に踊り出しました。
舞天がある屋敷を訪問したとき、家のなかに位牌(いはい)(亡くなった人の霊(れい)をまつるため、お坊さんに付けてもらった名前を記す木の札(ふだ))があり、家主(やぬし)は涙を流していました。家主は舞天にいいました。
「どうしてこんな悲しいときに歌うことができるの? 多くの人が戦争で家族を失ったのに! 戦争が終わってからまだ何日も経っていないのに、位牌の前でどうしてお祝いをしようというのですか?」
すると舞天は答えました。
「あなたはまだ不幸な顔をして、死んだ人たちの年を数えて泣き明かしているのか。生き残った者が生き残った命のお祝いをして元気を取り戻さないと、亡くなった人たちも浮かばれないし、沖縄も復興(ふっこう)できないのではないか。さあ遊ぼうじゃないか」
彼の言葉に家主の表情が変わりました。
「集まりがあれば必ず顔を出し、場を盛り上げる変わった男がいる」
舞天の存在は水面にさざ波が立つように知られていきました。舞天は「ブーテン」の愛称(あいしょう)で親しまれました。
舞天の世の中を風刺(ふうし)した漫談(まんだん)に、みんなはおなかを抱えて笑いました。おなかのなかから大きな声で笑って、何だかみんなも少しずつ元気を取り戻してきました。打ちひしがれた人々の心が活力を取り戻し始め、舞天を中心に、地域の輪が広がっていきました。

人々の心を明るく照らしたブーテンの芸
舞天とともに民家をたずね歩いた照屋林助は、後にこう語っています。
「小那覇舞天は私にとっては先生です。先生は、夜になると『林助、遊びに行こう』と私を誘いに来ます。水筒に入った自家製の酒をチビリチビリ飲みながら家々を回ります。まだ起きている家を見つけると『スージサビラ(お祝いをしましょう)』といって入っていくのです。
当時は、一軒の家に一〇〇人くらいが詰め込まれて生活している状態でしたから、すぐに人の輪ができて笑いのうずが巻き起こりました。先生のつくり出す笑いは、希望を失った人々にとってどんなに救いになったか、計り知れないと思います。
先生、すなわち小那覇舞天という人は、自分が有名になるとか、偉くなるとかいうことにはまったく興味を持たない、ただ、どうしたら人を楽しませることができるのか? ということばかり考えている人でした。人を喜ばせる、人に喜んでもらうことが自分にとっての一番の喜びだったのです。
それは、笑いというものが、どんなときでも人の心をなごませ、勇気づけるものだからではないでしょうか」(「てるりん自伝」より)
【出典、参考文献】
石川市商工会ホームページ/沖縄タイムス記事/「てるりん自伝」照屋林助
なるほど納得の「ヌチヌスージサビラ」。
沖縄にはこんなすごい人がいたんだなー、私って本当になにも知らないなーと。
笑いって人を元気にしますよね。
今回の東日本大震災に被災された方に、遠く離れた沖縄からではできることは少ないですが、この気持ちが少しで届いていればいいなと思っています。
もちろん義援金もね。少しずつですが続けていこうと思ってます。

HY、サンボマスター、モンゴル800などなど豪華メンバー勢揃い!
私はHY→知名定男さん→マルチーズロック→神谷幸一さん→モンゴル800→神谷千尋さん→登川誠仁さん→下地勇さん→新良幸人さん→玉城千春さん(kiroro)→BEGINという流れで観ましたよ。
ていうかあまりにも豪華メンバーが揃い過ぎて、どこのステージに行こうか迷いまくりました。
最後のBEGINさんでは出演アーティストが全員参加して「島人ぬ宝」を大合唱。そこで「ヌチヌスージサビラ」という言葉を聞いてどう言う意味なのか気になっていたのです。
その後調べると、これは戦後の沖縄で活躍した「小那覇舞天さん」の言葉で、「命のお祝をしましょう」という意味でした。
ちょっと長いのですが、詳細を下記に転載しますね。
沖縄県の石川市(いしかわし)は、沖縄本島のほぼ中央にあって、第二次世界大戦後、沖縄で最初にできた市です。それまでは、美里村字石川(みさとそんあざいしかわ)といって人口二〇〇〇人足らずの静かな農村でした。戦争が終わった昭和二十年(一九四五年)、米軍によってここに難民収容所(なんみんしゅうようじょ)が設置され、沖縄各地から戦火に追われたたくさんの人々が集まりました。そのため、石川の人口は数ヵ月で三万人にふくれ上がり、石川市となったのです。
けれども、市になったからといって人々の生活が楽になるわけはありません。人々は、戦争で受けた心の傷を癒(いや)す間もなく、その日その日を何とか生き延びることで精一杯でした。軍の作業に駆り出され、食料と物資を手に入れることに追われて、疲れきり、毎日希望を失ったまま暮らしていました。

そこに突然現れた風変わりな男、それが小那覇舞天(おなはぶーてん)でした。
舞天は本名を小那覇全孝(おなはぜんこう)といい、沖縄県立二中(今の県立那覇高校(なはこうこう))を第一期で卒業し、その後日本歯科医学専門学校(現日本歯科大学)を卒業した歯科医でした。
舞天は仕事で白衣(はくい)を着ているときや家にいるときは、それこそまじめで口数の少ない人でしたが、一歩外に出ると風変わりな男に変わりました。
舞天は、弟子の照屋林助(てるやりんすけ)と毎晩のように、まだ起きている家を見つけては甲高(かんだか)い声で「ヌチヌスージサビラ(命のお祝いをしましょう)」といって入っていきます。「ジャカジャカジャン」と三味線が鳴り響き、歌が始まります。
突然やって来た中年の男が、その場でつくった歌を民謡(みんよう)の節に乗せ、この地方独特の踊りである琉球舞踊(りゅうきゅうぶよう)をくずしたヘンテコな踊りを舞うのですから、みんなはあ然とします。
しかし、やがて舞天のユーモラスな姿に乗せられ、みんなも一緒に踊り出しました。
舞天がある屋敷を訪問したとき、家のなかに位牌(いはい)(亡くなった人の霊(れい)をまつるため、お坊さんに付けてもらった名前を記す木の札(ふだ))があり、家主(やぬし)は涙を流していました。家主は舞天にいいました。
「どうしてこんな悲しいときに歌うことができるの? 多くの人が戦争で家族を失ったのに! 戦争が終わってからまだ何日も経っていないのに、位牌の前でどうしてお祝いをしようというのですか?」
すると舞天は答えました。
「あなたはまだ不幸な顔をして、死んだ人たちの年を数えて泣き明かしているのか。生き残った者が生き残った命のお祝いをして元気を取り戻さないと、亡くなった人たちも浮かばれないし、沖縄も復興(ふっこう)できないのではないか。さあ遊ぼうじゃないか」
彼の言葉に家主の表情が変わりました。
「集まりがあれば必ず顔を出し、場を盛り上げる変わった男がいる」
舞天の存在は水面にさざ波が立つように知られていきました。舞天は「ブーテン」の愛称(あいしょう)で親しまれました。
舞天の世の中を風刺(ふうし)した漫談(まんだん)に、みんなはおなかを抱えて笑いました。おなかのなかから大きな声で笑って、何だかみんなも少しずつ元気を取り戻してきました。打ちひしがれた人々の心が活力を取り戻し始め、舞天を中心に、地域の輪が広がっていきました。

人々の心を明るく照らしたブーテンの芸
舞天とともに民家をたずね歩いた照屋林助は、後にこう語っています。
「小那覇舞天は私にとっては先生です。先生は、夜になると『林助、遊びに行こう』と私を誘いに来ます。水筒に入った自家製の酒をチビリチビリ飲みながら家々を回ります。まだ起きている家を見つけると『スージサビラ(お祝いをしましょう)』といって入っていくのです。
当時は、一軒の家に一〇〇人くらいが詰め込まれて生活している状態でしたから、すぐに人の輪ができて笑いのうずが巻き起こりました。先生のつくり出す笑いは、希望を失った人々にとってどんなに救いになったか、計り知れないと思います。
先生、すなわち小那覇舞天という人は、自分が有名になるとか、偉くなるとかいうことにはまったく興味を持たない、ただ、どうしたら人を楽しませることができるのか? ということばかり考えている人でした。人を喜ばせる、人に喜んでもらうことが自分にとっての一番の喜びだったのです。
それは、笑いというものが、どんなときでも人の心をなごませ、勇気づけるものだからではないでしょうか」(「てるりん自伝」より)
【出典、参考文献】
石川市商工会ホームページ/沖縄タイムス記事/「てるりん自伝」照屋林助
なるほど納得の「ヌチヌスージサビラ」。
沖縄にはこんなすごい人がいたんだなー、私って本当になにも知らないなーと。
笑いって人を元気にしますよね。
今回の東日本大震災に被災された方に、遠く離れた沖縄からではできることは少ないですが、この気持ちが少しで届いていればいいなと思っています。
もちろん義援金もね。少しずつですが続けていこうと思ってます。
Posted by FP事務所エレファントライフ at 17:27│Comments(3)
この記事へのコメント
たとえば、うちなー噺家の藤木勇人さんも、自分の舞台で舞天さんの「ヌチヌスージサビラ」について語り続けていますよー。藤木さんは林助さんの弟子でもありますしね。魂は、引き継がれてます!!
Posted by natsuhiko watase at 2011年04月20日 01:30
at 2011年04月20日 01:30
 at 2011年04月20日 01:30
at 2011年04月20日 01:30命ぬ祝事さびら!かぁ!いい言葉だね!仮名表記にすると更に意味が伝わってくるね!
Posted by 本庄冬武 at 2011年04月20日 14:25
◆渡瀬さん
藤木勇人さんが語り継いでいるのですね。私って沖縄人なのに沖縄のこと全然知らなくていつも教えてもらってばかりですね(笑)
これからも色々教えてください♪
◆トム
うん、いい言葉だよね。こんな時だからこそ余計に胸に響いたよ。
この言葉がたくさんの方に伝わるといいなー。
藤木勇人さんが語り継いでいるのですね。私って沖縄人なのに沖縄のこと全然知らなくていつも教えてもらってばかりですね(笑)
これからも色々教えてください♪
◆トム
うん、いい言葉だよね。こんな時だからこそ余計に胸に響いたよ。
この言葉がたくさんの方に伝わるといいなー。
Posted by エレファントライフ トモリ at 2011年04月22日 23:25
at 2011年04月22日 23:25
 at 2011年04月22日 23:25
at 2011年04月22日 23:25※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。